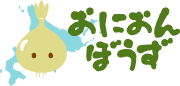野菜ソムリエの“薫る旬感”
冬至の準備OK~♪
もうすぐ冬至です☆ ~今年は12月21日(金)~   最近、特に暗くなるのが早くなったなぁ~と感じていましたが、来週にはもう冬至ですね! 最近、特に暗くなるのが早くなったなぁ~と感じていましたが、来週にはもう冬至ですね!わが家では、毎年必ず無病息災を願ってカボチャのいとこ煮を食べているんです。もしも当日に食べられなかったら、その前後には必ずね!という徹底ぶり(^_^)v なんでそこまで・・・?やっぱり、古くからの風習は大切にしたいですから。冬至にカボチャを食べると風邪をひかないって言いますからね♪ 冬至(12月22日頃)は二十四節気のひとつで、北半球では太陽の位置が1年でもっとも低くなる日なので、昼の長さがもっとも短く、夜の長さはもっとも長い日なんです。日照時間も短くなるので、お日様の出ている時を有効活用したいですね。 冬至は一陽来復(いちようらいふく)ともいい、陰がきわまって陽が帰ってくるということから、“新年が来ること。冬が終わり春が来ること。境から運が向いてくる転換の日”などの意味があるそうです。 ん?ということは・・・?そうなんです!この日を境にして、これから少しずつ昼の時間が長くなってきて、さらに!運気が好転していくと言うことなんですよね♪北海道はこれから雪が多く厳しい冬に向かっていくのですが、この言葉を聞いて、なんだか元気が出てきました0(^_^)0。 ~冬至で厄払い~ では、なぜ冬至にカボチャや小豆を食べてユズ湯に入るんでしょうねぇ~?  【ユズ】 【ユズ】いろんな説がありますが、冬至=湯治(とうじ)、ユズ=融通(ゆうずう)がきくという語呂合わせからきたとか・・・、一陽来復のために身を清めるとしてゆず湯に入ったとか。。。ユズの強い香りには邪気を払うという考えもあったようです。同じく二十四節気のひとつの端午の節句の菖蒲湯と同じ意味合いですね。 ユズにはビタミンCやクエン酸がた~っぷり入っているので、風邪の予防や美肌効果、疲労回復効果が期待されるほか、その香りはリラックス効果もばっちりなので、とても理にかなったユズ湯なんです。 昔の人の知恵ってすごいなぁ~!今みたいに入浴剤なんてない時代のはずなのに、すでにこれって入浴剤ですよね♪ 【カボチャ】 冬至にニンジンやダイコン、ミカンやキンカン、うどんなど“ん”のつく物を食べると運を呼び込むと言われ、縁起かつぎの意味があるともされています。 どうしてカボチャに“ん”?そうそう!カボチャはなんきんとも呼ばれていますよね。女子の好きな物の例えとして「イモ・タコ・ナンキン」なぁ~んて(*^_^*)。 でも、縁起かつぎだけじゃないんです!長期保存の効くカボチャは、野菜の摂れない冬の間、昔はと~っても貴重な栄養補給減だったんですって。ビタミンエース(A・C・E)の揃ったカボチャは、まさに理想的な食材のひとつだったんですね♪ 【小豆】 赤い色の小豆には、悪を払う陽力を持つと信じられていたそうですよ。そういえば・・・なにかと日本のお祝い事には、もちと小豆が欠かせないものとして登場しますよね。厄払いの冬至にもちゃんと登場していたんですね♪しかも!ポリフェノールもたっぷりでアミノ酸バランスもバッチリ!の小豆は、“色が赤いから”だけではなく、栄養も豊富なんです(^_^)v では、カボチャの「いとこ煮」ってどういう意味なんでしょう? こちらも色々な説があり、小豆などを煮た煮物料理で、かたくて煮えにくい材料から追い追い入れて行くことから、“おいおい=甥甥=いとこ”煮とかけたとか、同じ畑で採れた食材“親せき=いとこ”になったとか。。。昔の人は、おもしろい発想をしますよね♪それだけ食べることをとても大切にしていたんですね。  昔からの風習には、ちゃんと意味があって先人は生きてきたんですね。めんどくさいから、いいや!なんて思わず、それぞれの意味をきちんと理解したうえで、受け継いでいきたいものです。 昔からの風習には、ちゃんと意味があって先人は生きてきたんですね。めんどくさいから、いいや!なんて思わず、それぞれの意味をきちんと理解したうえで、受け継いでいきたいものです。私は、もう準備は完了しましたよ(^_^)v。あとは作るだけ♪ 小豆を煮る時間なんてないわぁ~。。。なんていう人も、スーパーなどでは小豆のパックや缶詰なども色々並んでいるので、とても手軽に出来ちゃいますよ。今年の冬至には、ぜひ!大切な人と一緒にカボチャのいとこ煮をたべてみてはいかがでしょうか?冬至ってねぇ~、いとこ煮の意味って知ってる?などと、楽しい会話をしながら♪ 食べきれずに残ったカボチャは、スープにしてよし!和風の煮物にしてよし!パーティーシーンに嬉しいパウンドケーキにしてもよし!バラエティにとんだ食べ方がありますので、毎日少しずつ食べて風邪予防して元気に年末を乗り切りましょうね0(^_^)0 野菜ソムリエ 木田靖代 2012/12/14 |