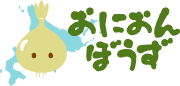野菜ソムリエの“薫る旬感”
節分☆なぜ大豆?
 節分といえば・・・豆まき♪ 節分といえば・・・豆まき♪  スーパーなどでは、色々な種類の豆が並び、「豆まき」の歌が繰り返し流れています。“おにはそと~、ふくはうち~、ぱらっぱらっぱらっぱら、まめのおと~♪・・・” スーパーなどでは、色々な種類の豆が並び、「豆まき」の歌が繰り返し流れています。“おにはそと~、ふくはうち~、ぱらっぱらっぱらっぱら、まめのおと~♪・・・”そう!2月3日は『節分』ですね♪「豆まきの日」とか「立春」などと曖昧にされがちですが、『節分』には“季節を分ける”という意味もあり、「立春」の前日に行われています。その昔は「立春・立夏・立秋・立冬」それぞれの前日に行われていたとか。。。江戸時代以降になって、「立春」の前日が『節分』となったそうです。 季節の変わり目に生じると考えられていた“邪気(鬼)”を追い払って、福を呼び込む「追儺(ついな)」という行事が豆まきの始まりと言われています。  さて、豆まきの「豆」は、なぜ大豆を撒くのでしょうか? さて、豆まきの「豆」は、なぜ大豆を撒くのでしょうか?「畑の肉」と呼ばれるほど良質のたんぱく質を含んでいて、栄養がギュ~ッと凝縮されているから?五穀のひとつだから?・・・いえいえ! 色々な説がありますが、“豆をぶつけて魔の目(まめ)を射ることで魔を滅する(まめ)”とされているそうです。背景にある昔の逸話も探して見るとおもしろそうですよ♪ さらに、必ず豆を炒ることには他にも理由があり、生の豆を撒いたあと、拾い忘れていた豆の芽が出ると縁起が悪いとされているからだそうです。なるほどぉ~!縁起かつぎからなんでしょうね(*^_^*)  ちなみに、北海道では「落花生」をまいて鬼を追い払います。 ちなみに、北海道では「落花生」をまいて鬼を追い払います。“え!?大豆じゃないの?”と驚かれることもありますが、北海道のほか、東北や信越地方でも落花生をまくことが多いそうです。 北海道でも、もともとは「大豆」をまいていましたが、昭和30年代ころから“掃除がしやすい”とか“物を粗末にしない”などの理由から、落花生がまかれているそうです。雪の上に落ちても探しやすいし、拾って殻を剥けばちゃんと食べられますものね(*^_^*) そんな落花生は、需要量の9割近くが輸入品ですが、日本でも大粒タイプのものが生産されています。商品の裏に貼ってある品質表示を見ると分かりますので、選ぶ参考として見てはいかがでしょうか。 歴史の浅い北海道も最近では、恵方巻きや鰯(いわし)を食べる風習も定着してきたようです。ケーキや和菓子などの恵方巻きの人気の高さにも驚かされます。思いがけないものが色々出ていて、まさに“イベントを楽しむ”という感じでにぎわっていますね♪ 本来の恵方巻きには、七福神にちなんで7種の具材“かんぴょう・しいたけ・キュウリ・ウナギ・卵焼き・でんぶ・ほうれん草(またはミツバ)”などと言われていますが、具材については、さまざまあるようです。昔からの風習の意味を考えると、節分をもっと楽しめるかもしれませんね☆ 今年の恵方は東北東なんだとか・・・。準備しなくっちゃ! 野菜ソムリエ 木田靖代 2014/1/31 |